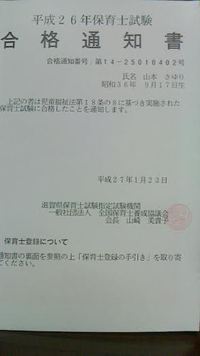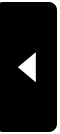2013年07月09日
思いがけない電話
昨夜、思いがけない方から、お電話を頂きました。
高校時代の担任の、国語の先生。
恩師です。
さあが、「風の歌」を書けるのも、この先生、あったればこそ。





思えば、私は幼少期、とんでもない「ほら吹き娘」だった。
周りの大人は、「空想と現実を、ごっちゃにしてる」と、言っていたが、
私の中では、空想と現実の区別は、ついていた。
人に喋る時も、「今は、空想の話をしている。」と言う、自覚があった。
だが、微に入り細に入り、実に、ありそうな事を喋る為、
聞いている大人が、「事実かも・・・」と、誤解してしまうのだ。
思えば、親も親戚も、随分振り回してしまった。
そんな私が、ぴたりと、ほらを吹かなくなったのは、小学3年生。
ひどいいじめを、受けていた頃だった。
友達はなく、休み時間は、担任の先生に纏わり付いて過ごした。
担任は、例の如く、ある事ない事、喋りまわる私に、
「考えた事を、『自習ノート』に書いて欲しいな。
忙しい時、最後まで聞けなくて、もったいないから。」
「自習ノート」は、宿題を出さない代わりに、毎日、家庭学習するための物で、
その代わり、絵を描いても、市販の問題集を切り取って貼り付けてもいい、
「自由ノート」でもあった。小ずるい一面のあった私は、
「考えたお話、書いたので、自習にしていいの?」と、念押しした。
「いいですよ」
実は、その前にも、考えた事を、書き留めた事はあった。
が、おませで耳年増だった私は、恋歌風の詩を、雑誌の付録の便箋に
書き散らした為、親に大目玉を食い、頭で考えた事を、文にしたためる事を、
厳しく禁止されていたのだ。どうも、色気過剰な子供だと、誤解されたらしい。
だから、公認の「自習」として、考えを「文にする」事は、楽しい「勉強」だった。
担任は、たくさん本を読み、言葉を増やし、美しい言葉を使うよう、教えてくれた。
当時のノートは、もうない。取り留めのない、断片ばかりだったように思う。
でも私は、ほらを吹かなくなった。ほら吹きの必要が、なくなったのだ。
そして、書いた物を、親に見せなくなった。
大人には種類がある。私を理解してくれる人と、してくれない人だ。
親と言えども、理解し合えない面はあると、9歳にして実感したのだ。
年月は流れ、私は、父親の転勤について、広島に引っ越した。
高校は、私立の女子高校に進んだ。そこで、生涯の恩師に出会ったのだ。
古典と現代国語を習った。特に古典。
「枕草子」「土佐日記」「古今和歌集」「万葉集」「百人一首」・・・・・・・
決して出来のいい生徒ではなかった。
少しばかりの記憶力に任せて、勉強しないからだ。
おまけに、夜中は毎日、小説を書いていた。遅刻の多い生徒だった。
類は友を呼ぶのか、クラス中、個性の激しい生徒が一杯いた。
このクラスから、「生徒会長」「副会長」「会計」が当選した。
「図書委員長」もいた。これが、私。
先生は大変だったと思う。ちなみに、後に、オペラ歌手まで出た。
その上、私が高校2年で、転校すると言い出した。
父の転勤だった。高校には学生寮があった。残ろうと思えば残れた。
両親は揺れた。父は、胃潰瘍をわずらい、食養生が必要だった。
単身赴任は出来ない。母は、私一人を広島に残そうとした。
折れなかったのは、祖母だった。
嫁入り前の女の子を、親元から離しては、縁遠くなると怒った。
同居の決まっている姑の、機嫌を損ねるのは、利口ではない。
間に立つ父の立場が、苦しくなる。
祖母は、私が電話で、あまりに生意気な喋り方をするので、所謂「不良娘」に
なってしまっており、同居させられないので、一人で残すと誤解したらしい。
父を責め、母を責めた。祖母の知る「娘」は、唯一、自分の娘。私の叔母。
世間擦れしていない、おっとりとした、大人しい人であった。
私は、兵庫県立の共学高校に転校した。
広島の女子高校に比べると、「格下」の感が、強かった。
方言が出るといじめられるのは、広島の中学で経験済みだから、
極力喋らなかった。喋るエネルギーは、書く方へ費やされた。
年月は、更に流れた。短大進学、就職、離職、再度の大学受験と失敗。
失意と結婚。3人の子育て。文を書く事は、遠くなっていった。
オランダへ、夫の転勤について行った。
ネーダーコールン・靖子という人を知った。
全身をがんに冒されながら、在欧の女性達の短歌を、まとめていた、歌人。
・・・こうなっても、人は、文を書くのだ。
真似をして、短歌を書いてみた。が、書けなかった。
何とか、小誌に投稿しようと、がんばったが、慣れない「みそひと文字」に
苦戦しているうちに、早や、帰国となり、その後、靖子さんは亡くなった。
安楽死だった。
少女向き小説の著者、氷室冴子さんも、未完小説を残して、亡くなられた。
グインサーガの著者、栗本薫さんも亡くなられた。グインがどうなったか、知る人はいない。
死の間際まで、書く人は書き続ける。ならば、適わぬまでも、書き続けよう。
そう思った私の頭脳に、啓示が降りた。
グインサーガのようなファンタジーを、書いて欲しいと言う、天の声だった。
「あんなに長くなくてもいい。きちんと終わりまで書いて欲しい。」
栗本薫さんが、どんな考えで、書かれていたかは、分からない。
ただ、私の心と頭を占領したのは、中学時代に作った架空の世界に、現れた、
「感情を持たない、黒い、粒子状生命体」と、5人のヒーロー達だった。
かくして、「風の歌」は、ブログ小説として、形を成した。
頑張って、書き続けよう。・・・でも、もし、誰も読んでくれなかったら?
私には、読んでくれる人の当てが、最低、一人いたのだ。
それが、先生だった。先生なら、読んで下さる。それを励みに書いた。
でも、東日本大震災が起こった。小説の冒頭と、景色が被った。
迷った。先生に誤解されたら、どうしよう。悩むうちに、2年が過ぎた。
思い切って、プリントして送ってみた。言い訳も、書き連ねてつけた。
そして、懐かしい、若々しい、優しい声の電話を頂いた。
涙が出た。34年ぶりの、お声を聞いた。
いっぱい喋った。幾らでも、話題が尽きない。
夜も更け、電話を切った。広島へ、行きたくなった。
懐かしいセーラー服。広い図書館。真新しかった講堂。
いつか行こう。近いうち。計画をしっかり立てて。たっぷり時間を取って。
「風の歌」のプリントを担いで。他の作品も、いっぱい担いで。
きっと行こう。決めた。決めたら、私は実行する。そう言う人間。
自分で完結できることは、絶対やる。だから、先生、待ってて下さい。
とりあえずは、「風の歌」を、完結させますから。
Posted by さあちゃん at 11:40│Comments(0)
│無題